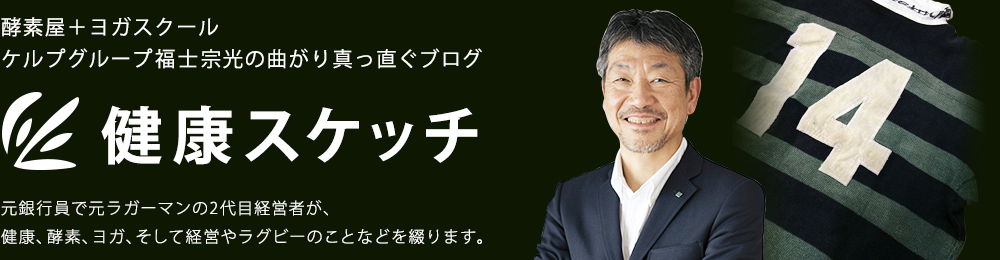産膜酵母のこと
酵素を製造するうえで幾つか増えて欲しくない微生物があるのですが、産膜酵母もそのひとつ。サンマクコウボと読みます。
たくあん漬け、味噌、醤油などの製造に関わる方はよくご存知かも知れません。
好気性(酸素が好き)の酵母菌で、名前の通り、液の表面に膜を張ったように増殖します。
毒性などは特にないとされますが、独特の臭いが出たり、風味を変えるので歓迎されません。
空気中に普通にいる菌なので、そもそも発酵室にはあまり人が立ち入らないようにするなどして、環境が乱れないようにすることがまず基本。特に発酵樽の蓋を開ける作業がある場合には気をつけなくてはなりません。
近年は当社発酵室に出現することはまずありませんが、発酵室を引っ越した直後とか、複数の人が出入りしたりした後に一部の樽がやられたことがあります。
もし発生してしまったら早めに表面をすくい取って除去するのが一般的。味噌やぬか床などでは少量であれば混ぜ込んでしまってもよいと思います。
普段からよくかき混ぜておくと発生しにくい(表面の酸素に触れている部分を中に混ぜ込んでしまう)。
健康上の危害はないと考えてよいので、仮に発生しても樽全体を廃棄するような必要はありませんが、独特の臭いは強くなるとシンナーのような感じがしますし、放置しておきますと膜の上に落下したカビなども増殖する可能性がありますから早めの対応が肝心です。
風味以外にも・・・
糖浸透圧抽出法・自然発酵という手法で製造する当社のF&E酵素は、発酵の初期に酵母が増えます。この酵母は産膜酵母とは別のものです。
この酵母は嫌気的(酸素がない)状態だとアルコール発酵といってアルコールを生成しますので、様々な酒を醸造するのにも活躍する酵母です。
一方、酵素の発酵においてはアルコールは生成しない方がよいので、好気的な状況が好ましい。そうすると酵母は酸素を使いながら糖を代謝し増殖します。要するに呼吸する訳です。
その後、酵母の糖代謝(呼吸)によって産生した代謝物を資化(栄養分とすること)して乳酸菌類が増殖を始めると考えられています。乳酸菌類は有機酸など様々は有効成分を産生します。
つまり酵母の好気的発酵は自然発酵のスタートとして重要なのです。
産膜酵母が増え液面に膜を張られたようになると、その下は嫌気的になってしまいます。
産膜酵母による風味劣化だけではなく、酵素の自然発酵の良いスタートのためにも避けたいものなのです。

酵母の好気的代謝(呼吸)によって炭酸ガスと水が生成します~産膜酵母の画像ではありません
この記事の投稿者
![]()
福士宗光
父から継いだ酵素製造と、自身はヨガ素人ながらヨガスクール運営を行っているケルプ研究所2代目経営者。
健康は食生活や適宜の運動を通じて自分自身で築き上げるもの。酵素とヨガでお手伝いすることが使命と考えています。